貿易創出効果
| 経済学 |
|---|
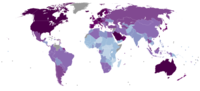 地域別の経済 |
| 理論 |
| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |
| 実証 |
| 計量経済学 実験経済学 経済史 |
| 応用 |
| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |
| 一覧 |
| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |
| 経済 |
|
|
|
貿易創出効果(ぼうえきそうしゅつこうか、英:The trade creation effect)は、自由貿易協定の締結などの自由貿易政策の結果、貿易が新たに生み出される効果[1]。
概要
この概念は、貿易協定などの自由貿易政策によって域外国との貿易が減少する貿易転換効果(英: The trade diversion effect)とともに、ジェイコブ・ヴァイナーの1950年の論文で初めて議論された[2]。貿易創出効果は、貿易協定などの自由貿易政策によって関税や輸入割当が撤廃され、非関税障壁も取り払われることで貿易コストが低下し、国際貿易が増える効果である。通常、自由貿易協定が締結されると、貿易創出効果と貿易転換効果の両方が生じる[3]。貿易創出効果による効率性の改善が貿易転換効果による効率性の損失を上回るとき、貿易協定は効率性を改善するものであると考えられる。
実証分析
欧州経済共同体(EEC)、ラテンアメリカ自由貿易連合条約(LAFTA)、経済相互援助会議(CMEA)の国際貿易への影響を推定した論文では、実際に貿易創出効果があったことが示されている[3]。
パネルデータを用いて重力モデルを推定し、国のペア固定効果、輸出国-年固定効果、輸入国-年固定効果を考慮して貿易創出効果と貿易転換効果を推定した論文がある[4]。貿易協定の締結がアナウンスされると、締結に対する期待(英: Expectation)から貿易が増える効果があることが示されている[4]。
スペインのデータを用いて、移民が増加すると移民の出身国との貿易が増加することが示されている[5]。また、貿易の増加は取引あたりの貿易額の増加(英: The intensive margin)よりも取引の増加(英: The exntensive margin)によって引き起こされていることも示されている[5]。
出典
- ^ “Trade creation”. Economics Online. 2017年12月9日閲覧。
- ^ Viner, Jacob (1950). The Customs Union Issue. Studies in the Administration of International Law and Organisation. 10. London: Stevens. OCLC 470257202
- ^ a b Endoh, Masahiro (2010) "Trade creation and trade diversion in the EEC, the LAFTA and the CMEA: 1960-1994" Applied Economics, 31(2): 207-216.
- ^ a b Magee, Christopher S. P. (2008) "New measures of trade creation and trade diversion" Journal of International Economics, 75(2): 349-362.
- ^ a b Peri, Giovanni; Requena-Silvente, Francisco (2010) "The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain" Canadian Journal of Economics. 43(4): 1433-1459.
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本概念 |
| ||||||||||||
| 理論・議論 | |||||||||||||
| モデル |
| ||||||||||||
| 分析ツール |
| ||||||||||||
| 結果 |
| ||||||||||||
| 貿易政策 |
| ||||||||||||
| トピック |
| ||||||||||||
| 近接分野 | |||||||||||||
| Category:国際経済学 Category:貿易 Category:国際経済学者 | |||||||||||||










